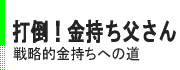|
 |
 |
青島ビール レポート |
「13億人の喉を狙え!!」
青島ビール(チンタオビール)
香港H株:0168 本社:山東省青島市香港中路五四広場青島ビール大廈1603
URL:http://www.tsingtaobeer.com
創業1903年の100年の歴史のある中国最大のビールメーカー、中国一のビール生産地である山東省青島市に本拠地を置いている
1993年に香港H株市場で初の国有企業株として上場を果たした
香港H株上場:1993年7月15日 発行価格:2.80HK 流通H株 346.85百万株(34.69%)
上海A株上場:1993年8月27日 発行価格:6.38元 流通A株 200百万株(20%) |
スポンサード リンク
主力製品の青島ビールは国内外市場で極めて浸透したブランドで、近年、吸収、合併を盛んに行い企業規模を拡大している。
2002年度の中国国内シェアは12.5%と、前年の11%から上昇させ、トップシェア。
2002年7月にバドワイザーで有名な、世界最大のビールメーカーである米アンハイザー・ブッシュ社と戦略・資本提携を締結し、将来的にはアンハイザーは同社の株式の保有比率を27%まで引き上げる計画である。
外資との提携では、99年からアサヒビールとの合弁で、深セン青島ビール朝日有限公司(青島40%、アサヒ60%)を設立し、中国において「スーパードライ」の出荷を開始。
また、00年から青島ビール朝日食品有限公司(青島35%、アサヒ、伊藤忠商事、住金物産)を設立し、ウーロン茶の生産を開始
海外進出の開始は1954年からであり、以来、50年の間中国のビール輸出の70%を占め、「中国産ビール=青島ビール」のイメージを確立している。
現在では香港、台湾、北アメリカを中心に世界40カ国以上の国々に輸出している。
02年の台湾への輸出開始で前年比61%増、アメリカ、欧州向けは横ばい。
世界中に点在するチャイナタウンでは、中華料理とともに青島ビールが人々の舌を満足させている。
・2003年までに世界のビールメーカートップ10入り、販売量360万トン
・2010年までに生産・販売量を800万トン規模の世界3位のビールメーカーを目指す
95年までは多くの国営企業同様、機敏な営業戦略が取れずに業績は低迷していたが、96年に李桂栄氏が社長に就任すると、実力主義が導入され、活気ある社風に変わりそれ以降業績は一変している
一時はライバルの燕京ビールに業界1位の座を奪われたが、積極的な買収戦略、徹底した品質管理、ブランド戦略により、業界トップに復帰している
2002年度のシェアは12.5%、販売量298万トン
参考:日本企業との比較
キリン340万トン、アサヒ280万トン、サッポロ110万トン、サントリー70万トン(01年度)
スポンサード リンク
- 【規模】
年間の消費量は2200万トン(2000年)で、2300万トンの米国に次ぐ世界第二位である。
ちなみに日本の消費量は約700万トンでドイツ、ブラジルに次ぐ第五位
また、中国人一人当たりの消費量は約17リットルと、日本人の三分の一、ドイツ人の九分の一に過ぎなく、市場規模は今後10年間で3倍に成長すると言われている
成長率は、過去十年で年率9%成長 過去5年は平均6%成長
市場の規模が大きくなるに従い成長のペースは落ち着いてきている
中国における一人当たりの年間消費量は大瓶換算で毎年一本のペースで増加している
2005年までに中国人の平均年間飲料消費量は現在の10キログラムから20キログラムに増えると予測されている
- 【現状】
国産400メーカーと外資が入り乱れている状況だが、このうち90%以上は生産効率や品質が悪い年間生産量が5万トンに満たない中小メーカーで、全メーカーのうち47%が赤字である
中国のビールには3つの価格帯がある
6元以上のプレミアム価格帯、2元台の中価格帯、2元未満の低価格帯
このうち一瓶5元(1元≒14円)以下の安価なビールが全体の90%を占め、外資系企業は高級志向がたたり苦戦を強いられている
また、中国全土の生産容量は需要に対して約2倍という供給過剰の状態が続いていることにより、ビール業界の利潤は年々下降しており、市場でのシェア確保のために価格競争が行われ、少なからぬメーカーは手段を選ばず赤字覚悟で販売しており、中でも中小メーカーは日に日に厳しい状況に追い込まれている
ただし、高等級の市場では、国内のほとんどのビール企業は優良とは言いがたく、人前に出せるようなビールはいくつもない(少なくても日本人には飲めないほど不味い)
一方、外国ラベルのビールが主導的地位を占める高級市場におけるシェアは比較的小さく、ホテルやクラブなどでの売値も10元〜15元で、それらの市場でのシェアもわずか5%に過ぎないことから、高等級ビールの市場の開拓余地は十分にあると考えられる
これらに伴い、ここ数年は変革が起きている
青島ビール、燕京ビール(北京エンプラの子会社)、華潤ビール(チャイナリソーシスの子会社)の3社が買収に次ぐ買収を重ね、シェアを急激に拡大している
その結果上位10社のシェアは、98年の21%から、01年には45%になった
今後も業界の淘汰は続くものと思われる
ちなみに北京では燕京ビール、上海では三得利(サントリー)がトップブランドである
01年度シェア
青島8%、北京燕京6%、中国華潤5%、広州珠江3%・・・・・・
- 【大きな流れ】
もともと中国のアルコール市場は、伝統的な白酒が大きなシェアを占めていたが、開放政策によって生活様式が欧米化し、低アルコールで飲みやすいビールやワインなどのシェアが伸びてきている。
日本でいえば、アルコール度の高い日本酒がビールや発泡酒に押されている状況と同じであり、理解できる流れだと思われる。
また、外国ラベルのビールは、苦味のあるコーヒーのような味がして中国の消費者はあまり好まないという評判である。
| |
売上高
(百万元) |
営業利益 |
純利益 |
総資産
(百万) |
純資産
(百万) |
総発行
株式
(百万株) |
株価
(HKD) |
配当 |
EPS |
BPS |
ROE |
PER |
PBR |
株主
資本
比率 |
売上高
純利益率 |
| 1998年 |
1,597.8 |
|
111.3 |
|
41.7 |
|
4,065.0 |
2,371.4 |
900.0 |
2.1 |
0.0 |
0.046 |
|
2.6 |
|
1.8 |
45.3 |
0.8 |
58.3 |
2.6 |
| 1999年 |
2,253.2 |
41.0 |
128.1 |
15.1 |
40.7 |
-2.5 |
5,263.8 |
2,308.3 |
900.0 |
1.2 |
0.0 |
0.045 |
-2.5 |
2.6 |
-2.7 |
1.8 |
26.6 |
0.5 |
43.9 |
1.8 |
| 2000年 |
3,448.3 |
53.0 |
208.6 |
62.9 |
63.9 |
57.1 |
7,000.5 |
2,270.3 |
900.0 |
2.1 |
0.1 |
0.071 |
57.1 |
2.5 |
-1.6 |
2.8 |
29.6 |
0.8 |
32.4 |
1.9 |
| 2001年 |
4,723.9 |
37.0 |
276.7 |
32.6 |
83.5 |
30.7 |
8,212.6 |
3,072.6 |
1,000.0 |
2.8 |
0.1 |
0.083 |
17.7 |
3.1 |
21.8 |
2.7 |
32.9 |
0.9 |
37.4 |
1.8 |
| 2002年 |
6,195.2 |
31.1 |
521.1 |
88.3 |
222.5 |
166.5 |
8,883.1 |
3,185.4 |
1,000.0 |
5.2 |
0.2 |
0.223 |
166.5 |
3.2 |
3.7 |
7.0 |
23.1 |
1.6 |
35.9 |
3.6 |
※この決算表は、おっさんが独自に調べたものなので絶対正しいとは言い切れませんが、ほぼ正しいと思っています。特に、総発行株式数については正直、本当に正しいかわかりません
※株価は同年の4月末付近のもの
まずは、皆さんの気になる味について♪
おっさんは、実際に中国に訪れた時、いわゆる三大ビール(青島、燕京、華潤)を飲みましたが、青島ビールが断然おいしかったです!(夏にオススメ!)
味としては、日本のビールに比べると苦味が少なく、フルーティーな感じで、おっさんの知る限りでは女性に飲みやすく、人気です♪
正直、燕京・華潤は青島と比較すると明らかに味が落ちています。
個人的には、特に燕京は飲めたものではありませんでした。
しかし、民族が異なると当然、味覚も異なりますので、おっさんの感想はあてにならないと思いますが・・・
もちろん、おっさんの味覚がおかしい場合もあります・・・
青島ビールは日本でも頻繁に見かけますので(アサヒが販売している)、投資する前にご自分で試飲してみて下さいね♪何気に病みつきになるかもしれませんよ♪
ちなみに、一部のセブンイレブンで取り扱っているのを発見しました!
今後、日本でも人気が出るのでしょうかね?
では、おっさんの独り言はこのぐらいにして、本題に入りましょう♪
スポンサード リンク
◎ 判断ポイント
- ビール市場全体はまだまだ成長傾向
- ビール業界は淘汰が進む(買収戦略で青島に有利)
- アンハイザーとの戦略的提携は、世界最大のメーカーに評価された証
- これからは低価格戦略は通用せず、ブランドの確立が勝ち残りへの道!(青島ビールは中国一のブランド)
- 外資にはわからない中国人の味覚を知っている
長期的に見れば、青島はこれまでのように、順調に買収を繰り返しトップシェアに君臨するだろうと、予想できると思います。また、中国でのビール消費量もドイツの水準(現在の9倍)まで伸びるかは懐疑的ですが、少なくても日本の水準(現在の3倍)までは市場は拡大していくものと思います。
しかし、問題はそこで起きてくる!と、おっさんは思います。(想像と言ってもよいかもしれません)
市場全体の伸びが無くなった時、さらに価格競争が激しくなるでしょう。
その時に「青島ブランド」が運命を分けます。
果たして中国の人々は、青島ビールが他のビールよりも価格が高くても青島ビールを選んで飲むでしょうか?
これはまさにバフェットの言う、「消費者独占型企業」になれるかどうかではないでしょうか。
つまり、青島ビール=コカコーラになれるか?と、いうことです。
今後青島は、短期的なシェアだけを求めて買収を行ったり、長期的な戦略として、ビールを売るのではなく、青島ブランドを売っていくというビジネスにして行かねばならないのです。
ブランド確立の面では、アンハイザーとの提携はプラスに働いていくのではないかと思っています♪
青島ビールのビジネスは、ブランドさえ確立してしまえば、ハイテク企業のように毎年苦労して獲得した利益のほとんどを研究開発費に投資しなくては企業が継続させることができないビジネスモデルではありません。
順調に成長していけば、株主にやさしい企業になってくれることと思います♪
ではでは、成長性の予測はこれぐらいにして、株価水準などの分析に移りたいと思います♪
| 割安性 |
2003年8月8日終値の株価は6.8HKで、PER32.4、PBR2.13となっています。
現在の株価水準は過去5年間で最も高い水準です。 |
| 健全性 |
株主資本比率は5年前の62%と比べると02年度では、35%と低下しています。
これは、レバレッジを効かせて積極的な買収戦略を行った結果です。 |
| 収益性 |
ROEは5年前の1.8%から、7.0%と改善しています。 |
以上を総合的に判断しますと、長期的には投資適格銘柄だと考え、現在の株価水準でも投資しても長期的には問題ないと考えますが、リスクを減らし、リターンを増やすためにも、何らかの影響で株価が安くなった時に拾っていこうと考えています。
|